昨日は二十四節気、
一年で夜が一番長い冬至でしたね。
今日は、こないだから自分の中でちょっと気になっていた
ナワラタナ→9つの天体→日本→九曜曼荼羅のさわりを
偶然、冬至とも重なる話だと知り
自分への備忘録として綴りたいと思います。
人の運命を司っている九曜星の供養をし、
一年間の幸福を祈り、災いを除く星祭が
昨日の冬至には日本各地で行われたことと思います。
星祭とは、人間の運命は天体の運行と深く結びついていると考えられ、
星を供養することにより、運勢を好転させようという信仰で、
星が最も長く天空にある冬至の日が、星供養あるいは星祭りに
もっともふさわしい日だと考えられました。
また、 星の運行は狂いないことから
交通安全、旅行安全、不変恒久、カリスマ性
にご利益があると言われています。
それから余談ですが、キリストの誕生日とされるクリスマスも、
冬至の行事が関係しているそうですよ。
この九曜星の考え方はインドから中国へ、
インド天文学やインド占星術が扱う9つの天体と
それらを神格化した神のことを仏の姿に当てて九曜曼荼羅として信仰し、
日本にも伝えられてきました。
ナワラタナで使用する宝石もこの同じ9つの惑星の配置を表します。
木火土金水の五惑星に太陽と月にを合わせたものが七曜。
九曜のうち七曜は実在する天体で、七曜にラーフとケートゥを合わせたものが九曜です。
ですが、ラーフとケートゥも古代インドでは実在する天体と考えらています。
太陽 スーリヤ (千手観音)
月 チャンドラ (勢至)
火星 マンガル (虚空蔵)
水星 ブダ (弥勒)
木星 ブリハスパティ (薬師)
金星 シュクラ (阿弥陀)
土星 シャニ (聖観音)
ドラゴン・ヘッド ラーフ (不動明王)
(月の昇交点)
ドラゴン・テイル ケートゥ (釈迦)
(月の降交点)
星や天体は狂いなく不変に宇宙を巡り、
その規則性に神を見出した古代の人たち。
宇宙の中心となれる壮大な力を感じ、
もっと宇宙とつながっている実感を得たいですね。
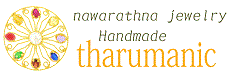



コメント